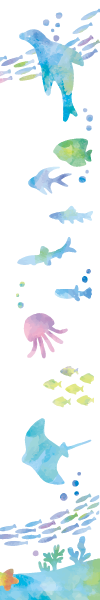|
|
●学年クラスの近況【昭和40年度卒業】
|
2022年12月17日 掲載
|
|
運動会今昔物語(昭和40年度卒業 菊池 泰彦)
十一月三日と言えば、島の最大のイベント小学校大運動会です。
当日、振興委員(部落長)は、朝早くから地域の席作り、女の人は、宴会のもよくりで大忙しです。
少子化で児童数が減少し、分団対抗リレーはなっけごんなりましたが、「子どもは地域の宝」という想いで、皆が声援を送る光景は今も変わりません。
時代の流れとともに変化もあります。まんでも運動会の華である地区(部落)対抗リレーは、年代別でなく男女別五人の合計が百五十歳以上、わけーしゅがなっけとこは、二百歳以上男女混合でも走るようになりました。選手が見つからず不参加の地区が多くなってさみしきゃの~。 リレーが始まると、地区の名誉をかけた「燃える闘魂」が火花をちらし、興奮のあまり大漁旗を持って走って応援する姿は今もかわりんなっきゃよ~。
わがえの嫁が選手で走った時は、つぶりを上げて見られずん、完走できれば天国、ぶっころんで迷惑掛ければ地獄。まさにその時流れていた曲♪天国と地獄♪のようでした。
運動場が芝生になってからは足なかを使う人、コーナーで腕をグルグル回してとびる人はなっけごんなりました。後の相撲も楽しみだろうがの~。こづかいを握りしめて出店で買った、くじ付きの甘納豆はうんまからーの~。
昔は「うんがとうちゃん・かあちゃんはだいどう?」でその子がどこの子か分かったが、まんは、嫁がいろんな所からきているので分かりんなっきゃよ~。
弁当も楽しみだらーの~。まだまだ貧しく、苦しい時代だった昭和三十年代中頃、運動会は家族・地域の誰もが楽しみにしていた行事でした。普段は、梅干し弁当で我慢させていた家でも、家計をやりくりし、玉子焼きや島寿司などの入った特別の弁当を作りました。
そごんいえば同級生がコンビーフを初めて見て「きびがわりぃおがくずのごんだーの」と言った事が可笑しく、ひっかすれんなっきゃの~、そんな時代でした。
今の騎馬戦は、女子も参加で帽子を取る形式どうが、当時は男子のみ参加で相手の騎手を地面にぶっことすまでやりました。棒倒しでは、棒の上から地面に落ち、棒の下敷きになることもありました。そのため上級生下級生めんなで怪我をしんのうごん工夫し、協力し合って、日常の活動や遊びの中で、痛みや連携の大切さを肌で体感したものでした。
人とのつながりや自然とのふれあいの思い出が重なり、その地域は故郷になります。
わいらは何歳になっても、故郷のことを思い浮かべます。
故郷の風景、幼なじみとの思い出が、生きていくことの支えになっています。
子ども達のためによけ思いでの故郷をつくるのは、三根で育ったわいら大人の役割のように思います。
「ふるさとは遠くにありて思ふもの」という詩がありますが、思ふばかりでなく、ぜひふるさとへおじゃりやれ。三根会が地域との虹の架け橋になることを願っています。
|
|
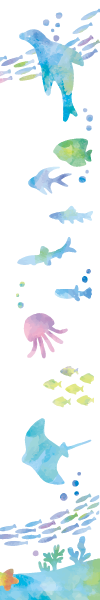 |
|