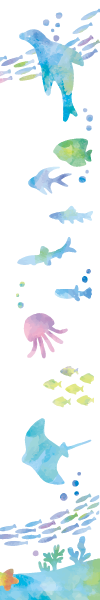|
|
●学年クラスの近況【昭和36年度卒業】
|
2022年12月13日 掲載
|
|
パンデミックの今と昔(昭和36年度卒業 八丈島三根会会長 峯元 信博)
この2年半余り、コロナ感染の拡大で我々の生活は一変してしまいました。いまだにコロナ感染は続いていますが、現在位置は以前に比べれば社会もだいぶ落ち着いてきたように感じます。世の中の経済や我々の生活もコロナ前に戻ろうとしています。
そんなパンデミックを経験した私たちですが、それでは昔の人たちの時代ではパンデミックはどのような状況だったのでしょうか。ここに八丈島での感染症の事例があったので少し紹介したいと思います。八丈島の古文書の研究者である「對馬秀子」先生の文書です。ここから少し引用して八丈島のパンデミックはどのようなものだったのか書き出してみたいと思います。
昔の感染症の主だったものは疱瘡(天然痘)で八丈島でも多くの感染症の事例がありました。八丈島みたいな隔離された島では本来、伝染病はなく、ほとんどが外来からで漂着船や江戸からの帆船だった、ということです。そしてその感染症は主に疱瘡であったそうです。對馬秀子先生のその古文書の研究資料では古い記録では1463年(寛正4年)正月より八丈島、小島共に初めて疱瘡流行し600人余り死亡とあります。
その後1641年(寛永18年)小島に疱瘡が流行53人病死との記録がありました。そして江戸時代が栄えていた中で、本土と八丈島の往来も活発になって人の行き来も増え、感染症の流行の機会も増えてしまったようです。
1711年の八丈島での死亡者285人、翌1712年に283人、その後も1865年までの間、幾度となく感染症の流行があり、島内の各地区で多数の死亡者が出たと言うことです。この時代より感染症対策は今と変わらず「患者を隔離し接触を避ける」という方法だったといわれています。「疱瘡を病むものをその土地に入れず、疱瘡のある所へは通行せず、まれにその毒に香触れて病むものは飛び疱瘡と名付けて村里を離れしところに小屋を作り,痘瘡を病みたるものに介抱を頼み、かさぶた落ちた後に家に帰る」。この時代でもこういった基本的な対策はあった、ということです。
その時代の八丈島でも伝染病が流行るとその地区や集落の通行を止めて遮断する、病人を隔離するという対策を行っていたということです。時には坂下で感染症が流行した際に集団で大賀郷などから数百人も坂上に避難した事例もあるそうです。そんな疱瘡の流行の中で他にも対策の一つとして、今でいうワクチンが江戸幕府から届けられた記述も残っているということです。
1723年「疱瘡妙薬牛糞黒焼仕法」が幕府からとどけられたとの記載も古文書にあったそうです。牛の糞を使った治療法です。牛や馬の糞で治療する。何か昔、聞いたような話ですね。
ではこのようなパンデミックの状況下で私たちの先祖の人たちはどういう生活を強いられてきたのだろう。昔の八丈島では飢饉の年も多く、通常の生活でも食料事情は厳しいものであった、と聞いています。島の人たちにとってそんな中での感染症の流行りは大変な苦難を伴った状況だったに違いありません。食物をきちんと手に入れられたのだろうか? 農作業、漁業、商売などできたのだろうか? 老人、子供たちへの影響はどれほどのものだったのだろう。この時代の八丈島の先祖の人たちに思いを馳せると、パンデミック襲来でその生活は今の私たちよりも数倍もの困難を極めたものだったのだろうと想像に難くなにありません。
このように昔の人たちも今と変わらぬ対策でパンデミックを乗り切ってきたのです。そして多くの犠牲者を伴っている点も今と変わらないようです。現在のコロナ感染の始まりでも八丈島での感染者は本土で流行したのち、しばらくしてから来島者からの感染で第一号の患者が出たのは周知のとおりです。
今回のコロナ感染拡大は現在(2022.9.30)、世界中で6億人以上の感染者が出ている。日本でも2千100万人以上の感染者数だ。外国では厳しい隔離制限が取られ、一時外出禁止措置まで取られた国もあった。中国ではさらに厳しく、多くの都市にロックダウンが布かれ完全に街が遮断されました。日本でも強制ではないがなるべく外に出ないように、無用な外出は控えるようにと都知事が毎日、テレビで訴えていた。人々は外へ出ないので外食産業をはじめ商業施設の店内は人影がなく、そして観光地などは閑古鳥が鳴いていた。夜の飲食街には特に厳しい制限が掛けられ、商売もままならない状況だ。多くの患者は入院、もしくは軽症者でも隔離生活を余儀なくされ長い間外出もできなくなってしまった。また、そのコロナ感染の対応に当たる医療施設は患者の増加に伴い、多忙を極めていた。
全国の病院、保健所などは毎日がパニック状態となり関係者は満足な睡眠時間もとれないほどの状態となっていた。そして養護施設や保育園、学校などの施設も神経質な対応を余儀なくされた。そして当然私たちの集まりも中止せざる得ない状況となって三根会総会も2年続けて2回も中止となってしまった。役員の打ち合わせもテラスのある店の外で会議をこなし、メールや携帯での連絡打ち合わせで済ませてきた。われわれの日常も制限され続けてきた。この間、スーパーやその他の出入りするどこの施設でもきちんと距離をとって並び、マスク必着だ。友人仲間との飲み会も未だにできず2年半も辛抱し続けている。ストレスがたまる一方だ。そんな状況下でも安全な場所でストレスを解消する場所はある。公園など外の自然環境の中で過ごせる時間を持つことだ。他にも山や海など、まさしく今こそ自然と戯れてナチュラルに過ごす時かもしれません。外でプレイするゴルフ場もこの間、賑わっていたらしい。コロナ下で自分も自転車で外出する機会が増えた。乗り物を使わず、自転車で行動する。遠くの公園や大きな商業施設まで遠出の外出なども自転車では可能だ。
マスク生活は今も日常の行動で必須条件のままだ。しかし、こんな収縮した世の中の状況下の生活でも昔のパンデミックと比べてみれば私たちの現実の生活はずっとましな方なのだ。家ではなんとかおいしい食事やビールは飲める。テレビや携帯のネットでの映画やユーチューブなどで楽しめる。安全な場所を選べば外出も可能だ。昔の人たちが耐え忍んだ生活とは打って変わって今は便利な機能的な生活環境があり、それなりに満足できる時代ではあると実感できる。
いずれにしても早くこのコロナ感染症の状況が終わってほしいと思うのは私だけではなく、みんなの切なる願いだと思う。
|
|
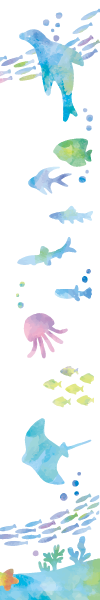 |
|