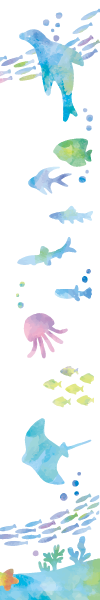|
|
●学年クラスの近況【昭和34年度卒業】
|
2022年12月19日 掲載
|
|
情け島(昭和34年度卒業 長沢 明美)
今年は御世が代わり、新元号となる第一回目の三根会です。昭和、平成、新元号。会長始め、役員の方々、各学年の幹事が「縁の下の力持ち」となり、長い年月を牽引、運営して頂いていることに感謝致します。私は新宿、品川、東京プリンス、中野、その四度の出席しかありません。それなので寄稿する立場ではないのですが…。テーマに迷った挙句、八丈島の代名詞でもある「流人」「情け島」と言うワードが浮かびました。三根会の会場に入るとそこには八丈島があります。暖かい八丈の空気があり、温かい人情があるのです。
昭和41年春、大切な人達に別れを告げ、18歳で上京しました。あれから50余年。いつの間にか71歳になりました。亡き母がよく言っていた言葉があります。「くには生き馬の目を抜く」上京して間もなく「ああ、来なければよかった!」と思い、ストレスで円形脱毛症となり帽子を編んだのも遠い昔の思い出です。
行き交う人々は温かい目なざしを持った島の人たちとは別の人間に思えました。島では、家から出ると「どけい行こ?」と声をかけてくれる顔見知りばかり。くには母の言う通りの世界でした。
物の本によると、流罪となった宇喜多秀家は、息子や家臣十数名を連れ八丈島へ流されました。亡くなるまでの50年間島の人たちに慕われ、温かくもてなされたそうです。八丈島が「情け島」と言われる所以です。
小説にも書かれました。難破した船の乗組員を助け、青ヶ島から八丈島を径て、手厚く保護され送り届けられた実話を元にした小説です。また、だいぶ以前のことだと思いますが、自分達のご先祖が八丈島民に助けられ、近年になり和歌山県と友好関係が結ばれた。これらのことは全て島民の温情ある人間性を称賛するものだと思います。この行為は今でも脈々と受け継げられています。自分の姉も登校拒否だった生徒を預かり、里親となり社会へ送り出しました。実母よりも強く、深く関係は現在も続いています。岡山在住の姪も、岡山城主だった秀家の父との関わりなどから、岡山と八丈の友好に尽力しています。
今では島に帰ることも少なくなりましたが、飛行機から見る八丈富士は「情け島」を象徴し、畏怖堂々としています。暖流、黒潮のおかげでしょうか。
|
|
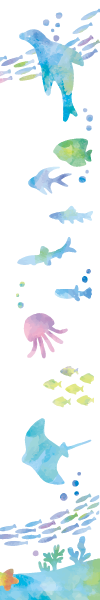 |
|