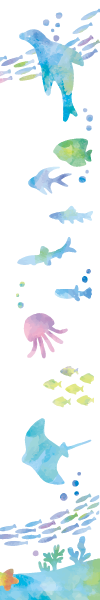|
|
●学年クラスの近況【会報編集局より】
|
2024年5月29日 掲載
|
|
八丈島の歴史の話(会報編集局より)
島民に影響を与えた漂着船
大海原に囲まれた八丈島は、大昔の頃より周辺の海を航海している船が嵐や事故にあって、島に漂着していた事実がある。そのような漂着船は過去にどのくらいの船が流されてきたのか気になるところです。
古い記録の一つに北条五代記による氏直の時代に3年に一度、秋に下田から北風に乗ってこの島に渡るとの記述があるという。確かに今の東京湾から来るよりは下田の方が距離的には近い。残念ながらこの記録の以前の時代の記録は見当たらないらしい。しかし、さらに昔に遡った時代からも漂着船が続いていたことは容易に想像できる。
その後、江戸時代、伊豆七島は幕府直轄の法定流刑地であったから、島民の自由な交通や交易はもとより、他の国地からの旅人の入島もできなかった。したがって、諸国の廻船や漁船も、漂着以外には島に近づくことはできなかった。この八丈島と内地を結ぶ唯一の定期船は官船であってその出船入りは島民にとって待ち遠しいものであったという。黒潮の流れに乗った漂流船はそのほとんどが点在する伊豆諸島を通過し、再び帰るすべもなく、むなし洋上に消え去ったことであろう。中には島々を眼の前にしながら、不運にも流れ去った船も多かったのだろう。八丈実記によると八丈島、小島、青ヶ島に漂着した船は記録されている1474年から1865年の間、約390年間に199艘を数える。それも寛保年間から明和年間に至る31年間の記録が欠如しているから、事実はそれよりもはるかに多かったであろう。特に多かったのは1850年(寛永3年)で一年間に27艘、300人以上の人々が漂着している。記録されたもののうち、はっきりしている180艘を分類してみるとその遭難時期は12・1・2月の3か月に7割近くが集中している。これは北西季節風によるものであって、台風による遭難はわずか11艘を数えるのみである。地方別では、大阪を含む摂津が48艘で最も多く、これに対して江戸船は11艘で、やはり西南日本の大藩の所在地が多くなっている。そのほとんどが江戸への上り船で、当時の太平洋側の海上交通の勢力関係を反映している数字といえる。
この当時、島に住んでいる人々にとって漂着船の積荷は何物にも代え難い貴重な救援物資であったという。島民は漂着船の来ることを望み、乗組員を精一杯歓待したのである。漂着船の積荷に関しては厳重な取り締まり規定があって、勝手に横領することは許されなかったが、島民と船頭との話し合いで、積荷の処分はかなり自由であったようである。当時の規定では漂着船の積荷の一割が島方のものになり、残りは再出航の時に積み込むことになっているが、船も破損している場合が多いので、島で買い取っていることが多かった。船員が死亡して着く場合や、船が沈没して積荷を引き上げた場合はその全部が島方のものになった。船が難破し岸に漂着した荷物は二十分の一が島方のものになった。城米船や藩船でさえ、漂着の時は積荷を島に与えたので、これに対する島民の歓喜は非常なものであった。元禄年間には、記録されている漂着船だけでも10艘以上あり、そのうち4艘からはこめ五百俵から千俵内外を陸揚げして、困窮している島民に配った、ということである。昔の八丈島では飢饉が頻繁にあったということなので漂着船の積荷の物品は島民にとって貴重なプレゼントになったようである。
|
|
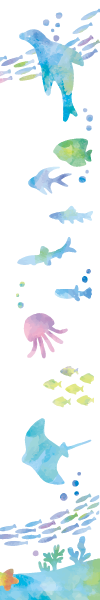 |
|